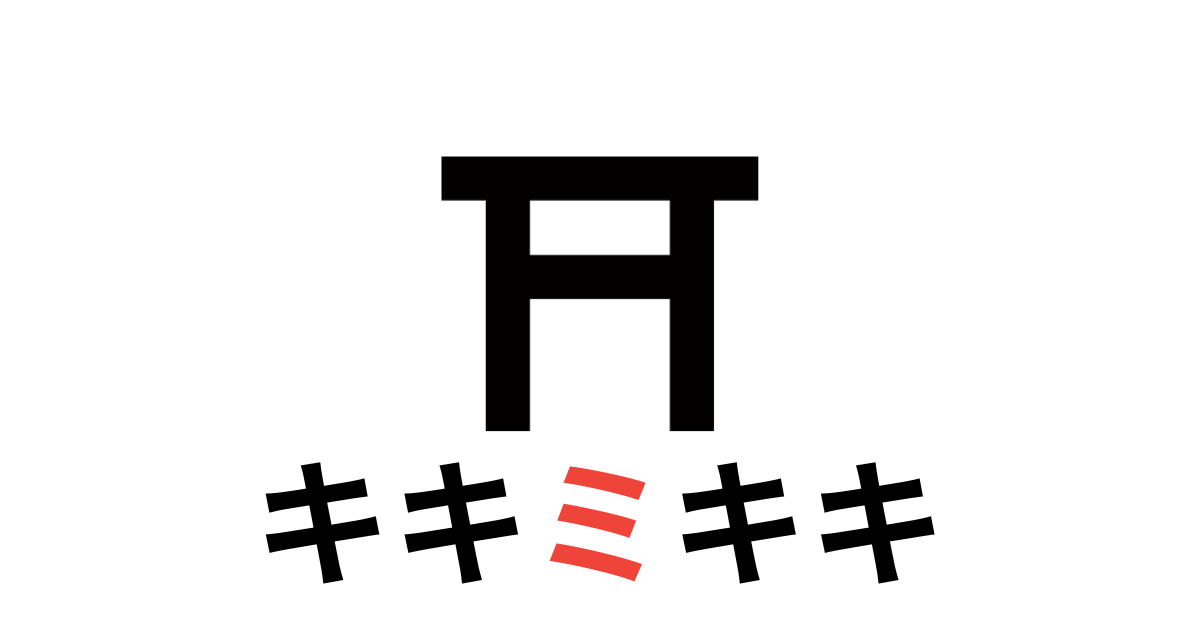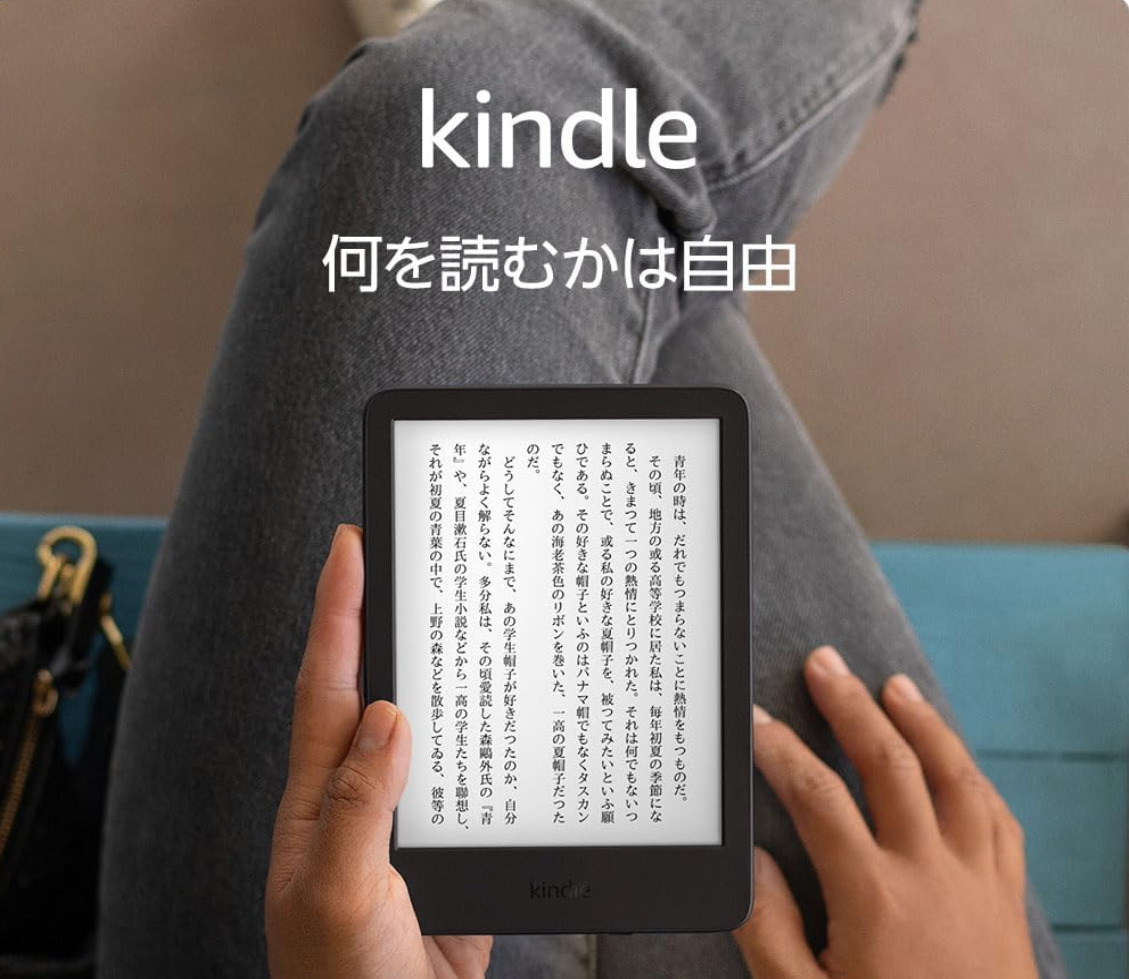6月の年中行事と古事記の神話のつながり

【6月の神話と神さま】古事記に登場する神々にまつわる行事・祝日・お祭りを紹介!
はじめに
6月は「水無月(みなづき)」と呼ばれ、梅雨に入り、湿度も高まり心身ともに疲れを感じやすい季節です。
しかし古来より日本では、この時期を「清め」と「祓い」の月とし、神道の教えとともに暮らしの節目として大切にしてきました。
本記事では、6月に日本各地で行われる古事記に関連する行事や祭礼を取り上げ、そこに込められた神さまの意味や、日常生活に取り入れたい習慣をご紹介します。
6月の年中行事と古事記の神話のつながり

夏越の祓と禊ぎの神事
6月といえば、もっとも重要な神事が「夏越の祓(なごしのはらえ)」です。
これは半年間の穢れを払い、残り半年の無病息災を祈る行事。
古事記では、イザナギノミコトが黄泉の国から戻った後に「禊(みそぎ)」を行う場面が登場します。
この禊こそが、現代の祓えの原型です。
神話の世界では、穢れを落とすことは神性の回復を意味します。
私たちも日々の生活で知らず知らずのうちに心身に積もった疲れやストレスを祓うため、この行事を意識的に取り入れたいところです。
梅雨と水神・罔象女神(みづはのめのかみ)
梅雨の季節は、植物や田畑にとっては恵みの雨の時期であり、水に対する感謝と共に注意が必要な時期でもあります。
古事記に登場する「罔象女神(みづはのめのかみ)」は、水の女神であり、井戸や川、雨水などすべての水源に宿るとされる神です。
水の神を祀る神社では、6月に雨ごいの神事や水神祭が行われることもあります。
家庭では、水回りを清めたり、感謝を込めて掃除することが、神話的な意味での「水との和解」にもつながります。
衣替えと清浄の象徴・天照大御神
6月1日は「衣替え」の日でもあります。
これは単なる衣服の入れ替えではなく、「身を清める」「心を入れ替える」という意味を含んでいます。古事記において太陽神・天照大御神は、清らかさと秩序の象徴とされています。
新しい服に袖を通すこと、古い衣類を丁寧に洗ってしまうことは、目には見えない穢れを払う行為ともいえます。
天照大御神のように、清らかで明るい気持ちで夏を迎えたいですね。
6月に行われる神話に関連するお祭り

茅の輪くぐりとスサノオ命
「夏越の祓」とセットで行われるのが「茅の輪くぐり」です。
大きな茅(ちがや)の輪をくぐることで無病息災を祈願するこの行事は、スサノオ命に由来するといわれています。
スサノオ命は荒ぶる神でありながら、人々を疫病から守る神として信仰され、疫神除けの神として多くの神社に祀られています。
スサノオを祀る神社では、6月に茅の輪神事が行われ、参拝者は左・右・左と輪をくぐりながら心身を清めます。
愛宕神社の火渡り神事とカグツチ神
火伏せの神を祀る愛宕神社では、6月に「火渡り神事」が行われます。
これは火の上を素足で渡ることで無病息災や災厄除けを祈願する神事。
古事記に登場する「カグツチ神(火之迦具土神)」は、イザナミ命を焼き殺してしまうほどの火の神であり、火災という恐ろしさの象徴でもありましたが、その後、火を制御する神として信仰されるようになりました。
火の力を「浄化」として受け入れる火渡りの神事は、まさに神話の転換点を現代に受け継ぐ儀式といえるでしょう。
水無月祓と全国の神社神事
6月30日前後には多くの神社で「水無月祓(みなづきばらえ)」が行われます。
「水無月」という言葉は「水の月」とも読まれ、神道では水の神々に祈りを捧げるとともに、半年間のけがれを祓い清める意味を持ちます。
この時期に行われる神事の多くは、古事記の「禊」や「祓」に通じており、神話的ルーツを現代に伝える重要な習慣といえます。
6月の自然と神々の象徴

田植えと宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)
6月は全国的に田植えが行われる時期。古事記には直接田植えの記述はありませんが、五穀を司る神・宇迦之御魂神(稲荷神)への信仰は、古くから豊穣を祈る農村で広がっていました。
稲の成長には水、土、太陽の恵みすべてが必要であり、それぞれに神が宿ると考えるのが日本の神話的世界観。田植えの際に神様へ感謝し、祈る姿勢は、古事記の神々が自然と共にあった生き方そのものです。
紫陽花と少彦名命(すくなひこなのみこと)
梅雨時期の花といえば紫陽花。
湿度の高いこの時期に咲く紫陽花は、人の心にやさしい癒しを与えてくれます。
癒しの神といえば、古事記では医薬と温泉、酒造りの神である「少彦名命(すくなひこなのみこと)」が有名です。
少彦名命は大国主命と共に国づくりをしながら、病気や心の不調にも寄り添う神として広く信仰されています。
紫陽花を家に飾ったり、体調を整える時間を意識的に取ることで、少彦名命の加護を感じられるかもしれません。
雨と雷と高御産巣日神(たかみむすびのかみ)
6月は雷が多くなる季節でもあります。雷は、古来「神鳴り(かみなり)」とされ、神の怒りや力の象徴とされてきました。
古事記では高御産巣日神が生命をつかさどる神として登場し、天候や自然界の動きとも深く関わります。
高御産巣日神の働きは「産霊(むすび)」すなわち生命をつなげる力です。
雨や雷といった激しい自然現象も、神の働きの一部と受け止め、恐れながらも敬う心を大切にしたいですね。
夏越の祓に向けて神棚と心を整える
神棚の清掃と御札の見直し
6月の終わりに行う「夏越の祓」は、神社での行事だけでなく、家庭内でも行うことができます。
まずは神棚の掃除をし、御札が古くなっていないかを確認しましょう。
穢れを取り除くには、まず“場”を整えることが大切。
清潔な空間で神札を祀ることで、神さまとのつながりも強くなります。
季節の植物で神棚に彩りを
6月らしさを演出するためには、紫陽花や笹など季節の植物を神棚の近くに飾るのもおすすめです。
自然のものは神さまが宿る場所とされ、色や香りによって空間が引き締まります。
また、茅の輪の小型版や和紙で作った「水無月飾り」などを添えるのも趣があります。
【神棚と節分】おみくじ置き「ミチシルベ」と御札立て「ヨリドコロ」のすすめ

おみくじを飾る「ミチシルベ」
おみくじを持ち帰り、その年の指針とすることはとても大切です。
「ミチシルベ」は、おみくじをおしゃれに飾れるアイテムで、神棚や玄関に置くことで運勢を意識した生活ができます。
御札を祀る「ヨリドコロ」
神棚やお札の置き場に困っている方には、「ヨリドコロ」がおすすめです。
シンプルなデザインながらも、神聖な空間を作ることができます。



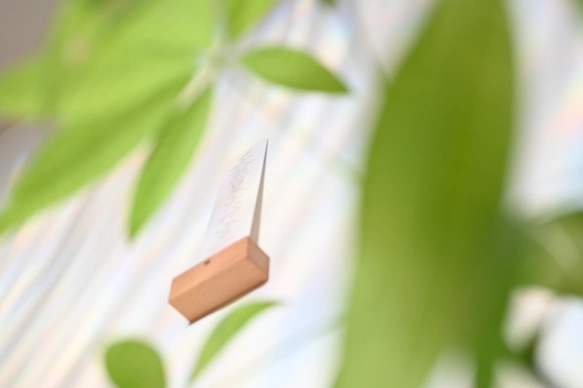


おみくじをお洒落に飾る『ミチシルベ』






神話を感じる暮らしを6月から始めよう
禊ぎと感謝の心を日々に取り入れる
6月は、体と心を浄め、日々を感謝と共に生きる大切さを再確認する月です。
古事記の神々のように、自然に感謝し、穢れを払いながら生きる姿勢が、現代の私たちにも必要です。
お祭りや風習を子どもと楽しむ
茅の輪くぐりや水無月の行事は、子どもにとっても楽しく、そして神話の世界を身近に感じる良い機会です。
絵本や神社巡りを通して、親子で神話の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
500万冊の電子書籍が読み放題!人気のマンガや雑誌はもちろん、『古事記』関連の書籍も豊富に揃っています。自然と神を結ぶインテリアとしての神棚
神棚は単なる信仰の場ではなく、自然と人、神と日常をつなぐ「よりどころ」です。
神話の世界観を暮らしに取り入れる第一歩として、神棚を整えることから始めてみてください。
おわりに
6月は、古事記に登場する神々の力を感じながら、自分と向き合い、家族と調和し、自然と共に過ごすためのヒントがたくさん詰まった月です。
「祓い」と「感謝」をテーマに、神話に学び、日々の暮らしに活かしてみましょう。
そして、神棚にふさわしい御札立て「よりどころ」「みちしるべ」を取り入れて、神さまを丁寧にお迎えする空間づくりをはじめてみてはいかがでしょうか。