
干支(えと)の読み方・順番・意味を完全解説!2026年の干支と年齢早見表付きで開運につなげる!
① 干支とは?その意味と由来
干支(えと)は、中国の古代思想「十干(じっかん)」と「十二支(じゅうにし)」を組み合わせた暦法で、古くから時間や方位、運勢を示す基準として使われてきました。
現代でも年賀状やお正月の会話など、私たちの生活に自然と息づいています。
干支の起源と歴史
干支の考え方は、約3000年前の中国・殷の時代まで遡ります。
もともとは暦を記すための記号でしたが、日本に伝わると「神話」「農耕」「風水」などと深く結びつき、縁起や運勢を表す指標になりました。
日本における干支の信仰
日本では奈良時代以降、干支は神事や方位除けに取り入れられ、特に神社では方位除け・厄除け・吉方祈願などに活用されてきました。
たとえば、伊勢神宮や出雲大社では、干支に基づく祭礼や方位の考え方が今も残っています。
十干と十二支の組み合わせ
十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)が組み合わさり、60年で一巡する「六十干支(ろくじっかんし)」を作ります。
このサイクルは「人生の節目」としても重視され、還暦(60歳)は「一度生まれ変わる」とされるのです。
干支が示す人生のリズム
干支は単なる年の数え方ではなく、性格や運気の流れを示す「人生のリズム」でもあります。
古事記の神々が自然の循環を尊んだように、干支もまた天地のエネルギーの流れを表現しているのです。
開運の鍵としての干支
お正月に干支の置物を飾る風習も、年神様を迎えるための象徴的行為です。
神聖な空間づくりには、御札立て「ヨリドコロ」やおみくじ立て「ミチシルベ」を添えると、神様への敬意がより深まります。
② 干支の読み方と覚え方

click➡2026年の干支は「丙午(ひのえうま)」|性格・開運・神社・カレンダー情報
干支の読み方は、十干と十二支をそれぞれ正しく理解することが第一歩です。
「甲(きのえ)」「乙(きのと)」のように“え・と”で表現されるため、「干支=えと」と呼ばれています。
十干の読み方と意味
十干は自然のエネルギー「木・火・土・金・水」を表し、それぞれに陽(え)と陰(と)が存在します。
- 甲=きのえ(木の陽)
- 乙=きのと(木の陰)
- 丙=ひのえ(火の陽)
- 丁=ひのと(火の陰)
…というように、エネルギーの流れが干支に宿るのです。
十二支の読み方と順番
十二支は、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)という順番です。
これは古代中国の星座・方位の循環を基にしています。
覚え方のコツ
語呂合わせが効果的です。
「ね・うし・とら・う・たつ・み〜♪」と歌うようにリズムで覚えると、自然と身につきます。
また、おみくじに干支を対応させて運勢を楽しむのもおすすめ。
「干支をなぜ学ぶのか」
干支を知ることは、過去と未来の流れを理解することにつながります。
丙午のように“勢いのある年”を意識することで、行動や判断がより的確になります。
干支を暮らしに飾る
干支の置物やお札をインテリアに取り入れることで、自然と「祈り」と「感謝」を意識できます。
小さなスペースに「ヨリドコロ」を置けば、モダンな神棚としても映えるでしょう。
⛩️ おみくじ・御札の“よりどころ”【ミチシルベ/ヨリドコロ】
③ 干支の順番と物語
干支の順番には、それぞれの動物が登場する“競走の神話”があり、性格や運命の象徴として親しまれています。
干支の順番の由来
昔、神様が「元日の朝、私のもとに早く来た12の動物を、年の守り神にする」と告げました。
牛が早く出発し、鼠が牛の背に乗って1番に到着したことで「子」が最初になったのです。
順番に込められた意味
この順番には「努力」「知恵」「忍耐」「協調」といった人間の徳が表現されています。
また、古事記に登場する神々の性格とも重なる部分が多く、自然との調和を教えてくれます。
干支と性格の関係
生まれた干支によって性格の傾向があるとされます。
たとえば午年は「情熱的で行動力がある」、巳年は「洞察力が高い」など。
自分の干支を知ることは、自己理解の第一歩です。
干支を子どもと学ぶ
干支の順番を親子で学ぶことは、日本文化を伝える良い機会になります。
ヨリドコロのそばに干支カードを飾って、家族で楽しむのも素敵です。
干支を神話として語る
スサノオやアマテラスの物語と重ねると、干支は単なる暦ではなく「生き方の知恵」として輝きを増します。
④ 干支と年齢の早見表(2026年版)
干支を使うと、生まれ年から年齢を簡単に算出できます。
干支早見表(2026年版)
| 生まれ年 | 干支 | 年齢(2026年時点) |
|---|---|---|
| 1966年 | 丙午(ひのえうま) | 60歳 |
| 1978年 | 午(うま) | 48歳 |
| 1990年 | 午(うま) | 36歳 |
| 2002年 | 午(うま) | 24歳 |
| 2014年 | 午(うま) | 12歳 |
早生まれの注意点
1月1日〜節分前の生まれは、前年の干支になります。
たとえば2026年1月30日生まれの人は「乙巳(きのとみ)」です。
年齢と運勢の関係
還暦(60歳)は干支が一巡する節目。
このタイミングで「お札」を新調し、ヨリドコロに安置するのが吉です。
干支と健康運
年齢ごとの干支を意識すると、心身のリズムを整えるヒントになります。
2026年は火の気が強い年。心を鎮める木製インテリアが相性◎。
干支早見表を家に飾る
干支表をプリントして、ミチシルベのそばに飾ると運気アップ。
家族全員の干支を知ることで、絆を深める効果もあります。
⑤ 干支と性格・相性

干支で見る基本性格
干支ごとに性格の傾向があります。
例えば「辰年=リーダータイプ」「亥年=情に厚い」「申年=器用で賢い」など。
恋愛と相性
相性の良い干支は「三合(さんごう)」と呼ばれます。
たとえば、寅・午・戌の組み合わせは火の気を持ち、情熱的で相性抜群です。
干支別・人間関係運
チームワークを高めたい時は、相性の干支を意識すると良いでしょう。
丙午の年は勢いが強いため、調和を意識するのが吉です。
運気を整える風水インテリア
木と火のバランスを取るため、観葉植物+木製の「ヨリドコロ」や「ミチシルベ」を置くと、家庭内のエネルギーが安定します。
干支と名前・開運法
名前に干支の要素(辰・午など)を入れることで、運気の流れを呼び込みます。
⑥ 干支を暮らしに活かす:神社・おみくじ・風水

干支と神社の関係
多くの神社には干支にちなんだ守護神が祀られています。
たとえば京都の八坂神社(午)、出雲大社(亥)など。
干支別・おすすめの参拝時期
2026年は火の気が強い年。初詣や厄除けは早朝の参拝が吉。
木の香りがする神社は、丙午のエネルギーと調和します。
おみくじと干支運
おみくじを引いたら、結果を「ミチシルベ」に差し込んで毎日見返すのがおすすめです。
運勢を“習慣化”できるのが最大の開運法です。
御札の祀り方
神社で授与された御札は、「ヨリドコロ」に立てて飾ると気が整います。
木の香りが優しく、神棚を持たない家庭にもぴったり。
干支とインテリア風水
干支の方位(例:午=南)に対応する方向を意識して飾りを配置しましょう。
火の気を持つ年は、赤や橙をアクセントに取り入れると運気が上がります。
⑦ まとめ
干支は、時間と自然、そして神々をつなぐ“見えない糸”のような存在です。
2026年は「丙午(ひのえうま)」――火と情熱の年。
行動の年であると同時に、心の安定が求められる一年でもあります。
あなたの暮らしに、祈りとやすらぎを添える小さな道具――
御札立て「ヨリドコロ」とおみくじ立て「ミチシルベ」を取り入れて、
毎日の中に「日本の神様とのご縁」を感じてみてください。
それが、開運と調和への第一歩になるでしょう。
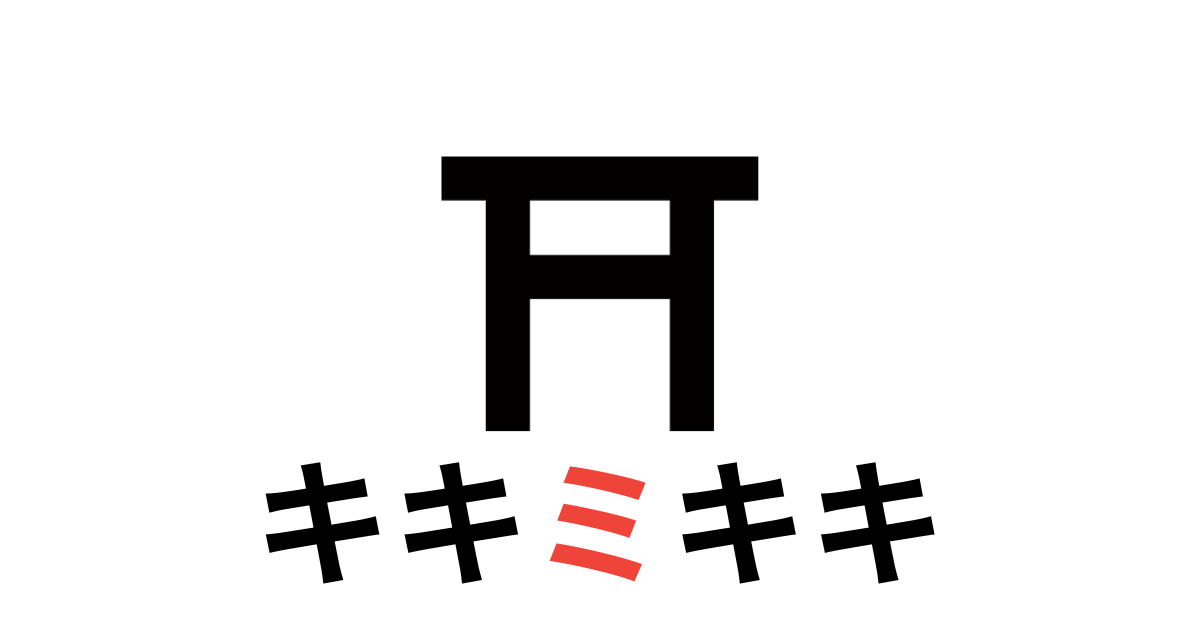
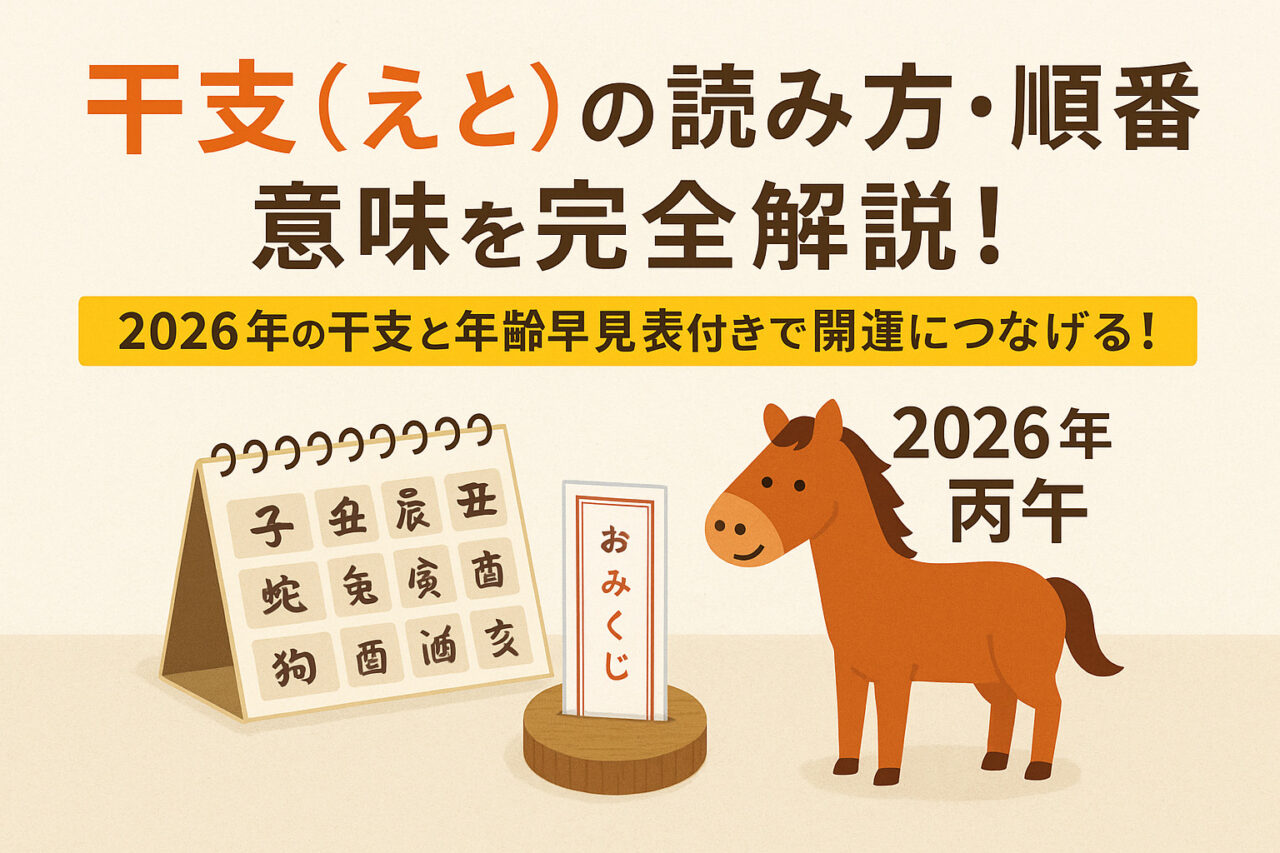


 🎐【ミチシルベ】おみくじ立て
🎐【ミチシルベ】おみくじ立て
 🕊️【ヨリドコロ】御札立て
🕊️【ヨリドコロ】御札立て





