
神社のお札の正しい祀り方|神棚がない家でもできる簡単な方法を解説します!
毎年の初詣や祈願で授与される「お札」。
多くの人が「とりあえず棚の上に置いておく」だけにしてしまいがちですが、
実はお札は「正しく祀る」ことで、よりご加護が強くなると昔から伝えられています。
この記事では、神棚がある場合とない場合の祀り方の違い、
神社とお寺の御札の扱い方、貼り方のコツまでやさしく解説します。
初めての方でもすぐに実践できる内容なので、安心して読み進めてください。
⛩️ おみくじ・御札の“よりどころ”【ミチシルベ/ヨリドコロ】
お札とは?神様をお迎えする“しるし”
お札は神様の分霊
お札とは、神社で祀られている神様の「分霊(ぶんれい)」を家庭にお迎えするものです。
家を清め、災厄から守り、家族の幸せを願うためのものとして古くから大切にされてきました。
お守りとの違い
「お守り」は個人を守るために持ち歩くのが基本。
一方で「お札」は家全体を守るものとして、神棚や清らかな場所に祀ります。
神社とお寺の御札
神社のお札は神様を、お寺の御札は仏様をお迎えするものです。
この2つは分けて祀るのが基本とされています。
お札を祀るときの基本ルール
お札の向きと位置
お札は「南向き」または「東向き」に祀るのが理想。
日の光が差し込む明るい方向に向けることで、神様が喜ぶといわれています。
目線より上に
神様を見下ろすことがないよう、祀る高さは「目線よりも上」にします。
本棚の上・壁面・玄関の高い位置などがよく選ばれます。
清らかな空間が大切
神様をお迎えする場所は、ホコリや汚れがなく、常に清潔であることが何より大切です。
毎朝、軽く一礼する習慣をつけるのもおすすめです。
神棚がない家でもできる祀り方

壁に貼る
神棚がなくても、お札は壁に貼ることができます。
方角はできるだけ南か東向きに。
賃貸の場合は両面テープや画鋲を工夫しましょう。
お札立てを活用
近年は、神棚を置けない家庭向けに「お札立て」を使う人が増えています。
シンプルなデザインのものを使えば、リビングや玄関にも自然になじみます。
👉 たとえば【いにしえ工房】の「ヨリドコロ」は、壁掛け可能な御札立て。
木のぬくもりとシンプルな造形で、インテリアにも溶け込みます。
避けたほうがいい場所
・床や低い位置
・トイレやキッチンなど水回り
・暗く湿気の多い場所
お寺の御札を祀るときのポイント
仏壇や専用スペースに
お寺の御札は、仏壇や専用の棚に祀ります。神社の御札とは別の場所が基本です。
神札と仏札は分ける
向かい合わせに置くと神仏がにらみ合うといわれるため、距離を離して設置しましょう。
線香・仏花を添える
お寺の御札にはお線香やお花を添えると、より丁寧なお祀りになります。
click➡2026年の厄除け神社おすすめ10選|福岡・東京・奈良など“最強”の開運スポットをご紹介
賃貸でも安心!お札の貼り方・設置アイデア
壁を傷つけない工夫
両面テープやマグネット式スタンドを使えば、原状回復も簡単。
跡が残らない素材を選ぶのがコツです。
インテリアになじませる
ナチュラルウッドや白木の御札立てなら、リビングに置いても違和感なし。
生活空間の中に自然と「清らかさ」を添えられます。
祀る習慣を暮らしの中に
朝の「一礼」や感謝のひとことは、心の整えにもつながります。
お札を飾ることは、目に見えない安心を得ることでもあるのです。
お札を祀るときの注意点とよくある質問
複数のお札を祀る場合
中央に最も信仰の深い神様のお札を配置し、左右に並べるのが基本。
重ねて祀るのはNGです。
古いお札の処分
年が明けたら授与元の神社や寺院へ返納し、お焚き上げしてもらうのが一般的。
郵送対応の神社も増えています。
形式より心が大切
正しい形も大事ですが、もっとも大切なのは神様や仏様を敬う「心」です。
暮らしに神様を迎える|いにしえ工房の御札立て






ヨリドコロ
・天然木を使った上質な御札立て
・壁掛け可能で神棚がなくてもOK
・玄関やリビングにも馴染むシンプルデザイン
👉 ヨリドコロを見る
ミチシルベ
・おみくじを挿して毎日の指針に
・コンパクトで飾りやすく、ギフトにも人気
👉 ミチシルベを見る
神札とともに暮らす
神様を暮らしに迎えることは、心を整えることにもつながります。
「神棚がないから祀れない」ではなく、「今の暮らしに合う祀り方」を選びましょう。
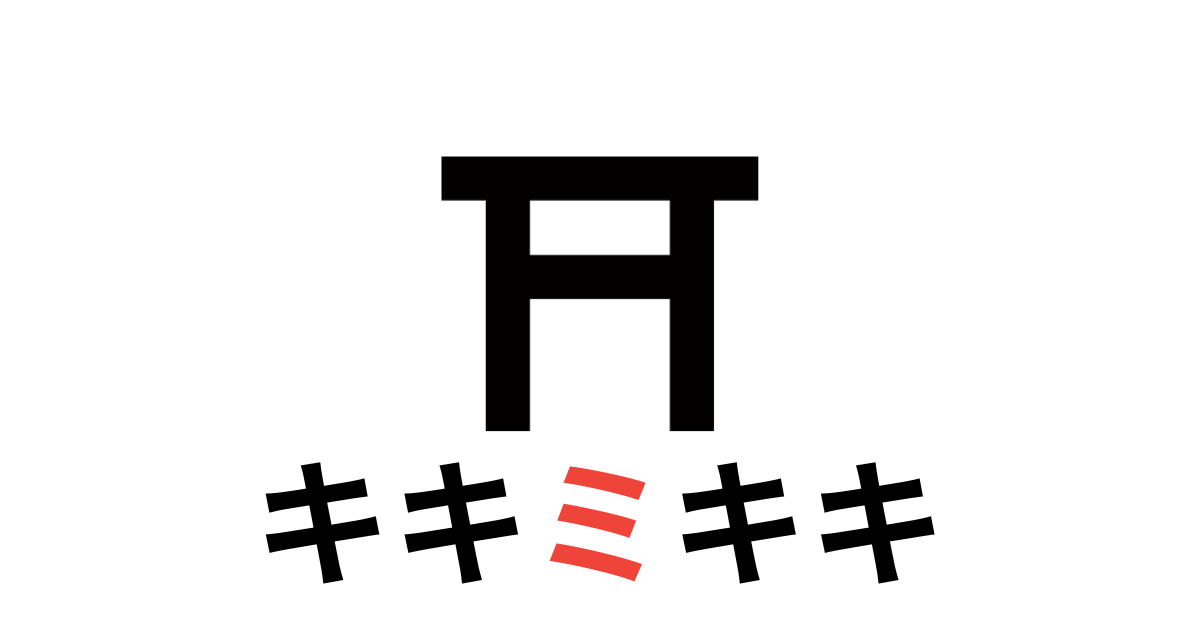

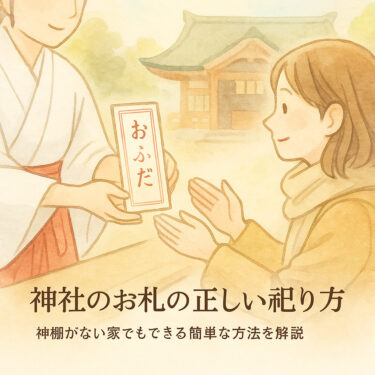
 🎐【ミチシルベ】おみくじ立て
🎐【ミチシルベ】おみくじ立て
 🕊️【ヨリドコロ】御札立て
🕊️【ヨリドコロ】御札立て







