
- 1 おみくじの順位を完全ガイド|浅草寺・熱田神宮・住吉大社の違いと「平・半吉・末吉」の本当の意味
おみくじの順位を完全ガイド|浅草寺・熱田神宮・住吉大社の違いと「平・半吉・末吉」の本当の意味
おみくじの順位は「大吉」から「大凶」までの並びが一般的ですが、
実は 神社や寺院ごとに順位の種類・割合が違う ことをご存じでしょうか。
この記事では、
- 日本で特に人気の浅草寺・熱田神宮・住吉大社の順位一覧
- 多くの人が誤解している「平」「半吉」「末吉」の本当の意味
- 日常でおみくじを活かす方法
- いにしえ工房の“ミチシルベ・ヨリドコロ”での上手な保管術
までを、分かりやすくまとめて紹介します。
1. おみくじの順位とは?基本と“聞き慣れない順位”の正しい意味






おみくじの一般的な順位の流れ(全国共通の基本)
多くの神社や寺院では、運勢は「良い → 悪い」の順に並びます。
一般的な並びは次の通りです。
大吉 → 吉 → 中吉 → 小吉 → 末吉 → 凶 → 大凶
神社によっては「吉」が最上位である場合もあり、
“どの神社のおみくじなのか”が順位を理解する鍵になります。
半吉・平・末吉の違いを正しく理解する(よくある誤解を整理)
普段聞き慣れない「半吉」「平」「末吉」。
これらは名前の印象だけでは理解が難しく、間違われやすい順位です。
- 半吉:吉と凶の中間。よい運気もあるが注意が必要という意味
- 平:運気はニュートラル。吉凶どちらにも大きく傾かない静かな状態
- 末吉:努力次第で運気が開けていく“これから良くなる”運勢
どれも悪いわけではなく、むしろ「行動次第で変えられる余白」だと考えられています。
神社ごとに順位の種類が違う理由とは?(歴史・流派の違い)
おみくじは、中世から続く「吉凶判断の流派」が神社ごとに異なり、
それが今の順位・種類の違いにつながっています。
浅草寺のように「観音百籤」を採用している寺院は種類が細かく、
神社本庁系の神社では比較的シンプルな順位になっていることが多いのが特徴です。
2. 浅草寺のおみくじ順位|凶が多いのは本当?理由は“平安の方式”にあり

浅草寺の順位一覧と特徴(観音百籤方式)
浅草寺は、平安時代から続く「観音百籤(ひゃくせん)」をそのまま採用しています。
そのため 凶の割合が約30%と高い のが最大の特徴です。
<浅草寺の主な順位>
大吉/吉/中吉/小吉/末小吉/末吉/凶
観光地で「凶を引いた!」と話題になるのは、この伝統が理由です。
凶を引くことは悪いことではない(むしろ行動のヒントになる)
浅草寺では「凶は行動の見直しを促す大切なサイン」とされており、
決して不運を示すものだけではありません。
「今は控えめに、しかし未来は開ける」という前向きな意味が込められています。
3. 熱田神宮のおみくじ順位|シンプルで分かりやすい伝統方式

熱田神宮のおみくじは“王道スタイル”(観光客にも人気)
愛知県の熱田神宮は、日本三大神宮のひとつ。
ここでは順位は比較的シンプルで “直感的に理解しやすい” のが特徴です。
<熱田神宮の主な順位>
大吉/中吉/小吉/末吉/凶
伝統的で分かりやすく、初めてのおみくじにもぴったりです。
学問・仕事・家庭運のアドバイスが実践的(迷いやすい年にこそ最適)
熱田神宮のおみくじは、仕事・学業・旅行・縁談などの助言が具体的です。
「運勢をどう行動に落とし込むか」を考えやすく、
新しい年の指針にする参拝者が多いのも納得できます。
4. 住吉大社のおみくじ順位|“反転”ともいわれる独自ルール

住吉大社の特徴:吉が最上位ではない特別な並び
大阪の住吉大社は「吉が最上位ではない」珍しい方式を採用しています。
<住吉大社の主な順位(代表例)>
大吉/吉/吉凶未分/末吉/凶
“吉凶未分”という独自の運勢があるのも特徴です。
吉凶未分は“これからどう転ぶかわからない運勢”
吉凶未分は、
「良い要素もあるが、丁寧に過ごすことで運が開ける」
という中庸の運勢。
未来が変わる余白のある順位であり、
慎重に過ごすべき期間だといわれています。
5. おみくじの順位比較図|平・半吉・末吉の違いを正しく理解する

順位の比較イメージ(理解しづらい3つを整理)
数字で覚えるよりも、関係性で覚えるほうが理解しやすくなります。
<吉の勢い>
大吉 > 吉 > 中吉 > 小吉
──超えられない壁──
末吉(これから良くなる)
半吉(上下に揺れる時期)
平(静かな状態)
凶(注意期間)
「平」は“悪くない”。むしろ安定の象徴という寺院も多い
「平=運勢がない」と誤解されがちですが、
寺院によっては「心が静かで整っている状態」を意味し、
吉凶判断をしない尊い運勢とされることもあります。
6. おみくじを日常で活かす|正しい保管方法と“ミチシルベ・ヨリドコロ”のすすめ
おみくじは持ち帰るのが現代の主流(毎日見返すことで意味が深まる)
最近は、神社でも“持ち帰って日々の指針にしましょう”という案内が増えています。
特に「凶・半吉・末吉」などのアドバイスは、
生活の中でこそ活かせる内容が多いためです。
おすすめの保管方法:いにしえ工房の「ミチシルベ・ヨリドコロ」
おみくじをキレイに飾り、常に見返せるアイテムとして人気なのが
ミチシルベ(おみくじ立て)/ヨリドコロ(御札立て) です。
- 北欧×和のデザインで玄関・デスクによく馴染む
- おみくじを傷めず立てて保管できる
- 家族の“運勢の共有”が自然に生まれる
「毎日見返して整える」という新しいおみくじ習慣をつくれます。
⛩️ おみくじ・御札の“よりどころ”【ミチシルベ/ヨリドコロ】
まとめ|おみくじの順位は“神社ごとの個性”。正しく理解すれば人生の道しるべに
浅草寺・熱田神宮・住吉大社は、それぞれ異なるおみくじの順位を採用しており、
その違いを知ることで「運勢の受け止め方」も深く理解できます。
- 順位の違いには歴史と流派がある
- 「平」「半吉」「末吉」は“悪くない運勢”で、むしろ行動次第
- おみくじは持ち帰って日常に活かすのが現代のおすすめ
そして、運勢を毎日そばに置くための小さな工夫として
ミチシルベ・ヨリドコロ の存在は、きっと役に立ちます。
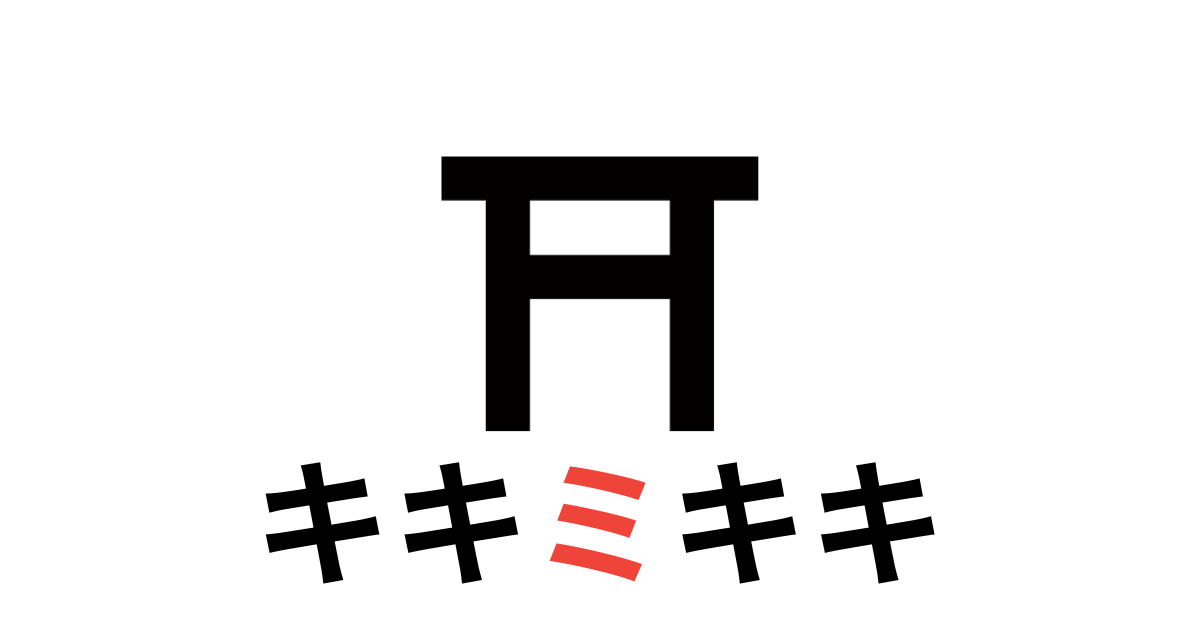



 🎐【ミチシルベ】おみくじ立て
🎐【ミチシルベ】おみくじ立て
 🕊️【ヨリドコロ】御札立て
🕊️【ヨリドコロ】御札立て









